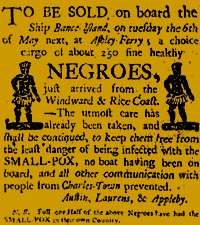小さいころに読んだ、あるいは読んでもらった絵本が一生の記憶として残ることがある。15歳以上であれば、『ちびくろさんぼ』という本が記憶に残っていない人は少数派であろう。なぜ15歳以上と言ったかというと、この本は1988年までは日本でも多くの出版社が発行していたのだが、この年から翌年にかけての短期間に、一斉に廃刊となり、それ以後に物心ついた15歳未満の子供たちは、この本を知らないことが多いからである。 『ちびくろさんぼ』は童話なのだから、当然フィクションである。しかし、その舞台のモデルとなったところがどこかといえば、インドと考えるのがいちばん自然であろう。なにしろ、物語には虎が出てくる。ライオンはインドにも少数ながらいるが、虎はアフリカにはまったくいないアジアの動物である。だから、主人公のサンボも、本来はインド人の少年がモデルだったと考えられる。しかし、この物語がアメリカに伝えられると、サンボはいつの間にか、アフリカ系の黒人となり、「サンボ」という名前もその文脈で考えられることになった。ヘレンが主人公にどのようなつもりで「サンボ」という名をつけたのかは、今となっては分からない。チベット系の人々に多い名前だという説もある。インドにはチベット系の人は多いので、頭からこれを否定することはできない。しかし、アメリカで「サンボ」というと、どうしても別の解釈が優勢になってしまう。アメリカには「ミンストレル・ショー」という一種の漫才があった。演じるのは顔を黒く塗った白人で、ひどく黒人を戯画化して演じていた。この時に「ボケ」役の黒人によくつけられた名前が「サンボ」だったのである。このため、すでに第二次大戦中から『ちびくろさんぼ』も黒人からの批判の対象となり、60年代の公民権運動の高まりの中で、本屋の店頭から消えていった。今日では、絶版にこそなってはいないが、一々注文しないと手に入らないという。 1988年、日本でこの本が廃刊されるきっかけを作ったのは、日本のデパートに黒人の特徴をひどく誇張したマネキン人形が置かれていることを報じたアメリカ紙『ワシントン・ポスト』の記事であった。これを読んだ大阪の堺に住む有田利二氏は、『ちびくろさんぼ』を出している出版社に軒並み手紙を書き、廃刊を訴えた。そして、最大のシェアを誇っていた岩波書店が真っ先に廃刊にしたのを皮切りに、各出版社が雪崩を打って廃刊に踏みきり、『ちびくろさんぼ』は書店から姿を消した。このときの廃刊がいかにも日本的な「自粛」によって、踏み込んだ議論もなしに行われたことがあとあと禍根を残すことになった。差別語への批判が盛んであった当時、最大の問題とされたのは、「サンボ」という名前であった。アメリカで、黒人がジャングルに住んでいるということ、絵が黒人を戯画化していること、ラストシーンで黒人の食欲が誇張されていることなどが問題にされていたのとは対照的であった。
1999年、「ちびくろさんぼ」は、硬派の出版社として知られる径(こみち)書房から、ちょうど十年ぶりに再刊された。絵は日本では初めてバナマンの原画に近い初版本の絵が採用された。再刊をめぐって社内で徹底的な討論を行い、その結果、この物語には差別性はないと認定したという。再版にあたっては、京都産業大学の灘本昌久助教授の働きかけがあったと考えられている。灘本氏は、著書でみずから書いているとおり、祖父母が四人そろって被差別部落の出身である。本人は部落の外で育ったものの、自分のルーツへの関心から、部落解放運動にも浅からず関わった人である。その人がなぜ、差別的とされたこの本の再刊に尽力したのかを私なりにまとめてみる。私のとらえ方の当否については、灘本氏がやはり径書房から出している『ちびくろサンボよ すこやかによみがえれ』と、本人のホームページを参照して正確を期されたい。
たとえば、いわゆる言葉狩りの問題である。自分の内面を点検して差別意識を克服することが大切だという主張には私も賛成する。「~は差別語だ」と言うだけの運動では、外から暗記を強いられるばかりで、このような機会は奪われてしまうと灘本氏はいう。しかし、それならば、「サンボ」という言葉がミンストレル・ショーに由来するものではない、ということばかりを強調する姿勢はいかがなものだろうか? 「サンボ」という語をアメリカの文脈でしか知らない黒人に、それこそ外から暗記を強いることにはならないのだろうか? これでは、「片手落ち」である。「手ぶら」や「舌足らず」まで差別語とするのを批判するあまり、「バカでもチョンでも」まで擁護しているのはどうかと思う。「チョン」の語源が朝鮮人ではないことには私も同意する。「ちょんの間」という言葉があるように、「ちょっと」という程度の意味らしい。しかし、なぜ「バカ」の方を問題にしないのだろうか? 人が思慮の足りないことをしたとき、それを「バカ」とか「アホ」とか言うことは許される。しかし、この場合は、「バカの一つ覚え」と同じく、明らかに知的障碍者のことをさしている。それに、単に「誰にでも」と言えばいいものを、わざわざ他者をけなすことで表現しようとするこのような表現は明らかに差別語といってよい。言葉によって傷つく人間自身が自分の主体を確立することは大事だが、だからといって、人を傷つける言葉を野放しにしてもよいということにはならない。「サルでも分かるパソコン入門」とか、「ネコでも分かる株入門」という本が出ているが、サルやネコとは違って人間は言葉で傷つくのである。灘本氏が差別の解消を願う人であることは分かるが、広く共感を得ようとするあまり、自分を抑えようとしすぎているようにも見える。
灘本氏が『ちびくろさんぼ』の廃刊を批判するのは、論議を通して問題を解決するのではなく、問題がなくなったかのように装うことによって問題の解決をいっそう困難にしてしまうということに尽きると思う。しかし、廃刊を主張する人たちが提起した問題を灘本氏が十分に受けとめているようには思えない。ストーリーの面白さを生かしてこの物語を救おうという試みは、いくつか行われている。物語の舞台を明確にインドとして主人公の名前も変えたり、舞台をアメリカ南部を髣髴させる架空の町としたり(黒人であるジュリアス・レスター氏)、主人公を黒犬にして題名を「チビクロさんぽ(散歩)」と変えたりといった試みである。これらの改作が筋立ての上でさまざまな無理を生じ、原作の味わいを損なっているという灘本氏の指摘には同感できる点も多い。しかし、だからといって何もかも元のままでいいということにはならない。私は廃刊に必ずしも賛成ではないし、再刊にやみくもに反対する気もない。しかし、絵や主人公の名前については、やはり考えるべきではないかと思う。『ちびくろさんぼ』が「すこやかに」生まれ変わるのでなくては、無条件で「よみがえれ」という気にはなれない。
| ||||||||
| 岩波版の「ちびくろサンボ」は、その後「瑞雲舎」という出版社から復刻版が出ている。 |