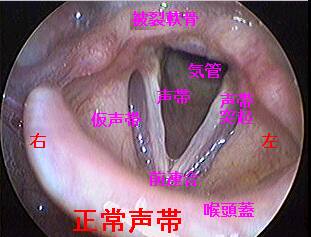日本語ではよく「濁る」「濁らない」という。この区別は英語などでいう有声音と無声音の区別と必ずしも同じではない。有声音とは声帯が振動する音であり、無声音とはしない音である。mの音は有声音である。のどぼとけ(女性の場合はそのあたり)に指先を当てたまま唇を閉じ、「ん~~」といって見れば、声帯が振動しているのが分かるであろう。同様に「あいうえお」と順にいってみれば分かるように、母音は単独で発音するときにはすべて有声音といっていい。しかし、唇を閉じ、母音を添えないようにしてささやき声で「プッ、プッ」といってみよう。指先は何も感じないはずである。「カ」も「ガ」も母音の「ア」の部分では声帯がふるえる。しかし、「ガ」「カ」と順にいってみると、「ガ」では最初から声帯の振動が始まっているのに対し、「カ」では少し遅れて始まるのが分かるであろう。有声音とは声帯の振動をともなう音であり、無声音とはともなわない音のことである。 日本語には、古くは語頭の濁音というものがなかった。今日でも、濁音で始まる言葉の大半は漢語か洋語である。濁音で始まるやまとことばは少なく、多くは「でる←いでる←いづ」「ばら←いばら」「だく←いだく」のように語頭の母音が落ちてできたものか、「ぶた」「どぶ」「どろ」などのように成立が新しく、俗語的な感じがするものである。そのためか、日本人は語頭の濁音を「汚い」と感じることが多い。「美肌(びはだ)になる」といわれると肌がざらざらになるように感じる人も多い。甲子園の優勝投手だった板東英二は決勝戦で、自分の名前が濁音で始まるので悪役になったなどといっている。このときの相手投手は「村椿(むらつばき)」という女性的な感じの名前であった。男の子にはよく「剛(ごう)」とか「「大輔」のように濁音で始まる名前がよくつけられるが、女の子の場合は、「ご」や「だ」という音は避けられ、濁音で始まる名前は「純子」など少数である。視力検査で「ま」に濁点を打った字が出て、まごついた上で、つぶれたような声で「ま」と読むCMもあるが、これは母音を[æ]と言っているに過ぎず、「ま」が濁っているわけではない。何となく汚い感じを表したのだろう。漫画の吹き出しには、「あ゛」という表記も見られる。「あ゛ーっ
!」だと、「ぎゃーっ!」というような叫び声となるようである。 日本人が語頭の濁音を身につけ、有声無声の区別をするようになったのは、漢語の影響であると考えられている。しかし、奈良時代には、万葉集の山上憶良の「貧窮問答歌」の中にある「鼻びしびし」のように、擬音語擬態語の場合は使われていたようで、そのことが有声無声の区別ができるようになる下地となったとも考えられる。ところが、日本語に有声無声の区別を伝えたはずの中国語には、今日この区別が方言にしか残っていない。日本語を学ぶ中国人が、発音の面で最も苦労するのが、語頭の濁音なのである。昔と立場が逆転したといってよいであろう。言語の系統としては中国語とはまったく異なる朝鮮語も、この点では同じである。しかし、このことは、中国語や朝鮮語に濁音がないということを意味するのではない。中国人や朝鮮人が日本語を話すとき、むしろ濁ってはいけないところを濁ることも多い。語の頭では確かに濁音が言えないが、語中の母音にはさまれたところなどでは、むしろ自動的に有声音になってしまうのである。そのため、「げた」は、「けた」ではなく、「けだ」となる。しかし、しゃべっている本人には別々の音を出しているという意識はない。濁るところ、濁らないところが決まっているのだから、同じ音だと考えているのである。 ここで、「音韻」という言葉を覚えていただきたい。「音韻」は、「音声」とは別の概念である。今日の中国語や朝鮮語では、KとG、PとBなどは、違う「音声」ではあるが、同じ「音韻」なのである。どの音とどの音とを同じとするか違うとするかは約束事であり、その約束事は言語によって違っている。人間の出す声は多様である。男か女か、若いか年寄りか、風邪を引いているかどうか、抜けている歯があるかどうかによっても違ってくる。声の細かい違いを無視しなければ言語は成立しない。「音韻」とは、その言語で同じ音として扱われる音声の集まりだとでもいえば、分かりやすいだろうか? しかし、より正確には、言語音に対して人々が共有しているイメージといった方がいい。 「音韻」としては同じであるが、「音声」として違うという例は、日本語にもたくさんある。「空気」というときの「ウー」と「数字」というときの「ウー」とは、「音韻」としては同じだが、「音声」としては別のものである。注意深く発音してみると、「数字」というときの「ウー」の方が舌が口蓋(口むろの天井)に近づいているのが分かるであろう。朝鮮語ではこの二つの音を別々の音韻とみなすので、日本語を表記するとき、「す」「つ」「ず」の母音は、他のウ段の音の母音とは別のハングルで表記されている。もっとも、この違いは、「数字」の「ウー」をも「空気」の「ウー」と同じように発音する関西人には分かりにくいかもしれない。関西人が「そうです」というと「そうですゥ」と聞こえることがある。これは、関東や九州ではこの位置では母音が無声化してほとんど脱落するのに対し、関西では無声化が起こらないためである。。中国語や朝鮮語には有声無声に代わる有気無気の区別がある。この違いは、日本語にもあらわれるが、日本人は全然意識していない。「音声」と「音韻」の違いを知る材料は、身近なところにも珍しくないのである。 | ||||